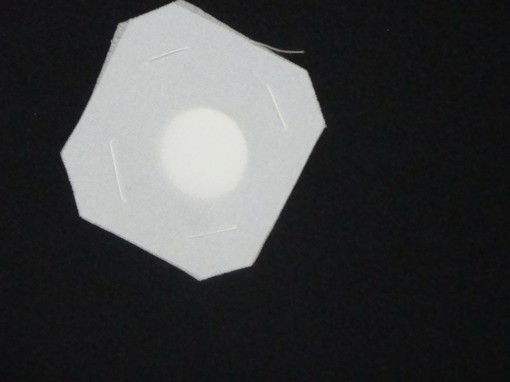紋をどのように意識するか(前編) 第一礼装の中で果たす役割
結婚式に掛かる費用の平均額は、352万8千円(2014年・リクルートマーケティングパートナーズ調査)で、お葬式費用は199万8千円(2010年・日本消費者協会調査)。
結構高く付いているのではないか、というのが私の率直な感想である。冠婚葬祭の簡素化が、この十年ほどの間に、かなりの勢いで進んでいると思われているが、この額を見れば、まだまだ相当の費用が掛けられている。
結婚式は、親族だけのレストランウエディングや、会費制のパーティ形式で行われることが増え、葬式は家族葬が一般化しつつある。では何故、これだけの費用がかかるのか。結婚式の場合は、少人数であっても料理の質を上げたり、衣装にこだわったりすれば、費用は増える。葬式は、寺へ支払う戒名料や斎場での経費というものが、たとえ家族葬であっても、極端に安くはなっていないからであろう。
さて、この冠婚葬祭に、親族が着用しなければならないキモノと言えば、当然黒留袖と喪服である。一昔前であれば、一族揃って着るのが当たり前だったものだが、式の簡素化や、生活様式の変化、さらにキモノに対する人々の考え方の変化などにより、「どうしても着用しなければならない」という意識は無くなったようだ。
結婚式で、新郎・新婦の母親が、二人とも留袖を着ていないことも珍しくなくなった。(大概、着るか着ないか、どちらかに合わせる。片方がキモノで片方が洋服というケースはあまり見られない)。葬式は、女性が喪主の場合でも、着ていないことしばしば見受けられ、妻や娘という故人に近しい立場であっても、洋服で済ませるが多い。特に暑い時は、それが顕著である。
さらに、たとえキモノを着たとしても、貸衣装で済ませる人が多くなっている。成人式もそうだが、結婚式や葬式という「式」と名が付く場所で、「もし、キモノを着るのであれば、借りればいい」という意識が、社会の中で高くなっている現実がある。
成人式の振袖はともかくとして(昭和30年代頃までは、振袖にも紋を付けていたが)、黒留袖や喪服には、必ず「家紋」が付いている。これは、紋を付けずに着用することが出来ないキモノである。そこには、第一礼装として、何よりもまず「家」を強く意識したものであることが、伺える。
今日から二回に分けて、フォーマルのキモノには欠くことの出来ない、「紋」について、「呉服屋の立場」から少し考えてみたい。「家の象徴として付いている紋」には、どのような意味があり、何を根拠として付けられているのか、その辺りを探っていくことにしよう。
まず今日は、フォーマルの中でも、第一礼装として使われる黒留袖と喪服について。
紋は、フォーマルのアイテムによって、付けられる位置や数も違い、職人が紋を入れる技法にも違いがある。最初に、第一礼装の品物は、どんな紋の入れ方がなされるのか、そこから話を始める。その中で、紋職人の精緻な技も、少し御紹介してみよう。
黒留袖と喪服。いずれも紋の位置が予め決められ、白く抜けている。この紋場のことを、石持(こくもち)と呼ぶ。
このような形態が取られているものは、上の二つの他に、男物黒紋付や男児祝着、そしてごく一部の色無地にも見られる。呉服屋では喪服そのもののことを、この紋場に由来して、石持と呼ぶことが多い。
第一礼装である黒留袖と喪服は、背・両袖・両胸と合計五ヶ所に紋が入る。上の黒留袖を見て判るように、紋を入れる石持のところは、汚れないように布で覆われている。
紋職人の正式名称は、紋章上絵師(もんしょううわえし)である。紋は、品物によって、技法が変わる。石持になっているものは、「上絵(うわえ)」というやり方で、紋が入れられていく。
これは、まず白く染め抜かれている紋場を洗い、紋の大きさに合わせて、下絵描きをする。この時に使われる型紙の材質は、和紙か樹脂である。うちの紋職人の西さんは、強度に優れ、吸湿性にも優れていることから、ポリプロピレンという樹脂を使っている。
出来た型紙は、石持に貼り付けられ、刷毛で染料を刷り込む。そして、竹製のコンパスや定規、さらには日本画で眉などを描く時に使う「面相筆」を用いて、細部を描いていく。この部分は、フリーハンドで描くので、職人それぞれの技量が試されるところだ。
どちらかと言えば、ポピュラーな紋の「丸なし下がり藤」。細部の葉脈の部分が、面相筆で描かれたところ。紋型紙は、破損しない限り何回でも使えるので、一般的な紋の場合、大概はすでに型紙が作り置いてある。めずらしい紋を依頼された場合には、型紙がないので、型を起こすところから仕事を始めなければならず、少し手間がかかる。
紋帳にも載っていない、極めて珍しい紋の「石持に右三つ巴」。先日、喪服の紋の入れ替えを希望される方から、依頼された紋。三十年呉服屋をやっている私も、初めて扱う紋である。もちろん、西さんでも今まで入れたことのない紋なので、型紙作りから始めなければならない。
「紋帳にない紋を入れる」というのは、決して珍しいことではない。こういう場合は、依頼されたお客様に、「紋の見本」を提示してもらう必要がある。この方は県外の方だったので、ご自分の家の墓石に付いている紋の写真を撮り、メールに添付して送って頂いた。以前は、ファックスで流して頂いたり、もっと前なら写真を封書で送ってもらったりしたものだが、便利な世の中になったものだ。
この「石持に三つ巴」という紋、難しいのは「三つ巴」の部分が影になっているところである。普通の巴紋ならば、白く染め抜かれた「陽(ひなた)紋」である。この紋は、巴の輪郭だけを白抜きしなければならず、紋型を起こすときに、大変技術を要する。
出来上がった紋を見ると、影になった三つ巴が均等になり、見事な出来映えである。西さんという職人は、もともと絵を志していた方なので、「紋の美しさ」には特別なこだわりを持っている。
喪服の下前の衿先には、紋場と同じように白く染め抜かれた部分がある。ここには、使う方の名前を入れる。喪服は真っ黒であり、親族は紋も同じことが多い。例えば、多くの人が同じ場所で着替えをした時なども、名前が入っていれば、すぐに自分のキモノと判別出来て、他の人のキモノと混同することが無くなる。この名前も、西さんがフリーハンドで描いている。
さて、このように職人の手で、丁寧に形作られてきた紋だが、その意味するところは、かなり様々である。まず、貸衣装に使われている紋から考えてみよう。
黒留袖にしても、喪服にしても、借りる人の紋をその都度入れ替えているということは、ほとんどない。かといって、何も紋をいれずに、白抜きした石持の状態では、着ることができないので、便宜的に紋を入れておく。
その紋は、「五三の桐」や「丸に鷹の羽違い」「丸に蔦」など、多くの家で使われている一番ポピュラーなものである。これは、紋の中でも、「通紋(つうもん)」と呼ばれるもので、正式な紋の代用とする要素が強く、いわば便宜的に使われているもの。
もともと紋は、公家や武家などの上流階級で、一族の象徴として発達してきたものだが、江戸期になると庶民にも普及し、自由に使えるようになった。中でも、「五三の桐」は、国や皇室紋として知られている「五七の桐」によく似た紋(桐の花びらが違うだけ)なので、その権威を真似ようとして、多くの人がこぞって付けるようになった。
貸衣装に「五三の桐」が多く使われている理由は、この紋が「通紋」として使われてきた経緯があり、かなり広く一般に普及したものだからである。
では、我々呉服屋が、日常の仕事の中で遭遇する「紋の問題」について、少しお話してみよう。
お客様が、喪服や黒留袖などの紋付のキモノを求められた時、付ける紋に悩まれることがよくある。例えば、娘が嫁ぐ際に喪服を作った時、入れる紋は実家のものにするのか、嫁ぎ先のものにするのか、よく相談を受ける。
紋は、地域によって捉え方が違う。旧来関西では、「女紋」が存在し、嫁いだ女性は、その家の家紋(つまり夫と同じ紋)を付けることが出来なかった。だから、女性は嫁ぎ先の家紋以外の紋を、独自に付けていたのだ。先にお話した、通紋の一つ「五三の桐」などは、代表的な女紋である。
嫁ぎ先の紋を付けられないとすれば、新たに通紋を付けるよりも、実家の紋をそのまま使う方が、ごく自然である。こうして女紋には、娘から子、そして孫へと同じものを使い続ける習慣が生まれた。
私も未婚女性が紋付を作る際には、ほとんどの場合、実家の紋を付けることをお奨めするが、これは関西の女紋の習慣から派生した考え方に基づいている。
では、関東ではどうか。関東にはほとんど「女紋」が見られない。家の紋は一つであり、夫も、嫁いできた妻も同じ紋を付けていた。これは、封建的な男性優位の家制度を象徴的に表しているものと言えよう。
この名残はまだかなり残っていて、うちのお客様が、嫁いだ後に作る紋付のキモノには、実家の紋ではなく、嫁ぎ先の紋を入れることがかなり多い。
このように、現在の紋は、関東と関西、それぞれの意識が混在して使われている。
時代と共に家制度が変わり、以前よりも家を尊重する意識が薄れているのは、事実である。特に結婚というものが、家と家を結ぶのではなく、個人と個人が結びつくものと考える人が多くなったことから、当然「紋に対する意識」も変わらざるを得ないと思う。
紋の仕事を承る呉服屋も、その意識に従い、出来るだけ自由度の高い「紋の選択」を、お客様に勧める方が自然であろう。但し、「こうあるべき」と決め付けるのではなく、あくまでもお客様の意思を尊重し、その中で今までの「紋の歴史」を踏まえた上で、アドバイスをしていくことが大切かと思う。
次回は、堅苦しい第一礼装のキモノではなく、もうすこし自由度の高い、訪問着や色無地、江戸小紋などに入れる紋について、お話することにしよう。
バイク呉服屋の家紋は、「五三の桐」なので、極めて一般的な通紋をそのまま家の紋にしたことが想像出来ます。ということは、家柄は由緒正しいものではなく、一般庶民だったことになりますね。
私には、関西の「女紋」のあり方が、今の時代には合っているような気がします。すでに今の時代、紋を嫁ぎ先と同じにする理由が見当りません。もっと極端に言えば、実家の紋を継承する必要も、無くなっているのかも知れません。キモノくらい、自分の好きな紋を自由に入れても、構わないように思えるのです。こんなことを書くと、保守的な考え方の方々からは、かなりお叱りを受けるかも知れませんね。
「家」というものには、多様な捉え方があり、それぞれ自分の意識に基づく考え方があるはずです。紋も、それと同様ではないでしょうか。
今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。