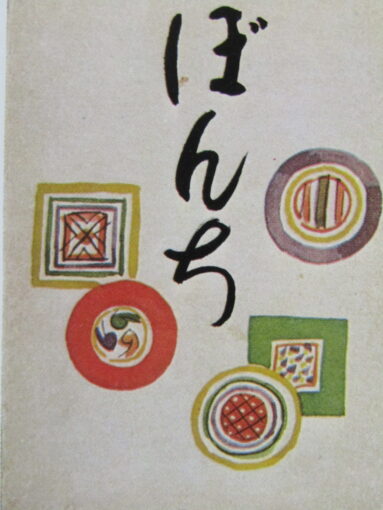型絵染と紅型 その魅力を探ってみる(後編) 「用の美」への意識
ここ数年、「金継ぎ(きんつぎ)」が静かなブームになっている。これは、破損した陶磁器を漆で接着し、そこに金や銀の粉を使って装飾を施し、修復させる技法。割れた箇所を継ぎ、欠けた部分を埋め、ヒビが入った所は補強する。古くは縄文土器の修復に、近くは桃山時代に茶器の修繕に用いた伝統的な技だが、使い捨ての時代と言われる今になって、こうして脚光を浴びることは、とても意外な気がする。
コロナ禍の巣ごもり需要もあり、家庭で手軽に出来る陶器の修繕キットは、かなり売り上げを伸ばしたらしい。また本格的に技術を学ぶ教室はどこも盛況で、金継ぎに関する認知度は、以前とは比べ物にならないくらい上がっている。このことから、深い愛着を持ちながら器を使っている人が、相当数世間に存在していることが判る。つまりそれは、「モノを慈しむ気持ち」が、未だに日本人の心の中に残っている証左と言えよう。
では、「直してまで使いたいモノ」とは、どのような質の品物か。例えば、それが器だとすれば、陶芸作家の手による芸術性が高い作品や、作り手のセンスが感じられる個性的なモノならば、使い手はやはり修復を考えるだろう。けれども、品物に対する愛着は、質の高さとは無関係なことも多い。それは使い続けてきた時間や、求めた時の経緯など、使っている人各々の「心持」によって生まれるものだから。なので、極めて安価なモノでありながら、金継ぎをしてまでも、直したくなるモノが出てくるのだ。
近代日本を代表する思想家・柳宗悦(やなぎむねよし)は、無名な職人の手で作る日常品に対して「美」を見いだす運動・民藝運動を提唱する。この新しい美の概念の普及は、後に日本民藝館という美術館を創設し拠点とすることで、運動を広げていった。
柳は、イギリスの思想芸術家・ウイリアムモリスの提唱した「アーツ・アンド・クラフツ運動」に影響を受けている。これは、産業革命以後のイギリスで、大量生産による安価な粗悪品が大量に出回っていたことを危惧し、中世の職人的な工芸の復活を提唱すると共に、芸術と生活の融合を目指した運動だった。柳の見出した美とは、民衆的な工芸、すなわち民藝における創造的な仕事。それはともすれば価値が低いとみなされ、一部では「下手物(げてもの)」と呼ばれていたような、風変わりで大衆的な器物を掘り出し、そこに焦点を当てることだった。
型絵染の先駆者・芹沢銈介は、柳が見出した美意識に深く共鳴し、共に民藝の道を進むことになる。主眼は「生活の中における美の追求」であることから、芹沢の仕事は多岐にわたり、その作品はキモノばかりではなく、身近な日常にあるモノとして出会える。今日はこれから、そんな芹沢の仕事を、「用の美」という観点からご紹介してみたい。
うちで所蔵している芹沢の作品「いろは文様・訪問着」。先代の私の父は、この品物を1977年(昭和52)年頃に求めたようなので、すでに半世紀近く店で持ち続けていることになる。当然のことながら、すでに商売のタネになるようなシロモノではなく、お蔵の奥に入って長く眠っている。
芹沢が、初めて沖縄の工芸品に出会ったのは、1928(昭和3)年のこと。この年、東京・上野で開催された国産振興博覧会において、沖縄の工芸品が特設展示された。芹沢は、そこで出会った紅型に強く惹きつけられたことが、後の仕事に大きな影響を与えることになる。「格好よく使いやすくなければ、モノは売れない。モノが売れなければ国は立ち行かない」との考えに立って設立されたのが、東京工業高等学校(現在の東京工業大学)の図案科である。1916(大正5)年にこの学校を卒業し、故郷静岡の工業試験場に就職した芹沢は、漆器や染織品、木工品の図案指導を行い、自らも懸賞ポスターに応募し、その図案は数々の賞を得ていた。そんな時に出会ったのが、柳宗悦であり、沖縄の民藝品であった。
芹沢銈介が没したのは、1984(昭和59)年の4月5日。享年88歳であった。上の画像は、亡くなって二か月後に静岡の芹沢銈介美術館で開かれた、追悼展のパンフレットと入場券。パンフレットには暖簾の代表的な文様・一本松文を使い、入場券にはいろは文様が描かれている。キモノや帯は言うに及ばず、本や冊子の装幀、団扇やカレンダー、店名入りマッチ箱などの身の回り品、さらに絵本に陶器にインテリアまで、描いた題材は多種多様で、とても紹介しきれたものではない。
染色作家でありながら、画家でもあり、デザイナーやイラストレーターのような側面も持つ「多面的な芸術家」。芹沢の作品からは、様々な領域を網羅した、そんな奥深い美的センスが感じられる。今回は、皆様にその端緒だけでもご覧頂きたいと思う。
(甕垂文 芭蕉布キモノ・1961年)
甕に釉薬が垂れた姿・甕垂模様を抽象的にデザイン化し、琉球芭蕉布の上に描く。
(苗代川文 水色地紬キモノ・1955年)
16世紀末、薩摩藩主・島津義弘が朝鮮に兵を進めた際、半島から連れ帰った名工たちの手によって開かれた薩摩・苗代川焼。芹沢は、この窯の風景をモチーフにしてキモノに描いた。
(柳文 金茶地紬帯・1931年)
この柳模様の紬帯は、芹沢の描いた型絵帯としては最も古く、1931(昭和6)年の作品。この年は、柳宗悦が「雑誌・工藝」を創刊した年だが、芹沢はその表紙の装幀を任され、当時の発行部数500全てを、型絵布を使って仕上げた。これが後に、数多くの装幀を仕事として請け負う契機になっている。
(雑誌・工藝の表紙 第17号と第67号)
先述した芹沢の手による「工藝」の表紙装幀。工藝は、1951(昭和26)年まで発行され、その数は120冊に及ぶが、芹沢が描くタッチは、最後まで変わることがなかった。使った挿し色は、弁柄色、鼠色、黄土色、そして藍色。和染めの基本となるこれらの色を、忠実なまでに用いた。
(山崎豊子著 「ぼんち」 ハードカバー本函・1960年)
(石野径一郎著 「守礼の国」 ハードカバー・1968年)
(海音寺潮五郎著 「西郷隆盛」 ハードカバー本函・1976年)
「工藝」表紙の仕事を終えた後、芹沢は多数の本の装幀を受けた。その多くは、しっかりと製本されているハード本のカバーや函のデザイン。本を丁寧に保管するための函(外箱)を、さりげなく美しく引きたてる。どれも、一目で「芹沢の作品」と判る。
社会派の小説家として知られた山崎豊子は、初期の頃は大阪・船場商人(あきんど)の生き様を題材にすることが多かった。「ぼんち」はその代表作の一つ。この函デザインのモチーフは、狂言の丸(紋尽くし)文様。石野径一郎は沖縄出身の作家で、沖縄戦を描いた「ひめゆりの塔」の作者として知られている。「守礼の国」のカバーデザインは、守礼門のシーサー。海音寺潮五郎は歴史小説をメインとし、NHKの大河ドラマでは、幾つかの作品の原作者となっている。西郷隆盛は、鹿児島出身の海音寺が、最もこだわりを持って執筆した人物。芹沢が函デザインに選んだのは、波文。
(宮城 鳴子温泉 鳴子ホテル マッチ箱)
(東京 台東区下谷 池の茶屋料理店 マッチ箱)
(東京・杉並区荻窪 いづみ工芸店 マッチ箱)
喫煙者の肩身の狭い今、タバコを自由に喫える店というのは、ほぼ絶滅しているだろう。しかし昭和の時代には、いつ何処の場所でも、多くの人が煙をくゆらしていた。そして多くの店では、宣伝も兼ねてオリジナルのマッチ箱を製作し、訪れる客に手渡した。百円ライターが生まれる以前、喫煙者にとってマッチ箱は必携品であったからだ。本のカバーもそうだが、このマッチ箱のデザインこそ、日常の中の美・用の美の最たるものだったように思える。
鳴子ホテルは明治六年創業の老舗。現在も伝統ある湯治文化を継承しつつ、立派な建物で営業されている。マッチのデザインは、鳴子名物のこけし。電話番号がひと桁の3番で、時代を感じさせる。ギリシャ風呂と記してあるが、それはギリシャ風建築の風呂ということなのだろうか。次の下谷・池の茶屋という料理店は、探したが見つからない。マッチに池之端の文字が見えるので、おそらく上野の不忍池のそばに店があったのだろう。最後のいづみ工芸店だが、現在もこのマッチ箱が製作された当時と同じ、荻窪のすずらん通りで営業を続けている。この店の先代店主・山口泉さんは、棟方志功を始めとして多くの工芸作家と交流があり、芹沢もその一人であった。そんな縁から、マッチデザインを依頼したと思われる。店は今、息子の浩志さんが受け継いでいる。
(東京 日本橋 ざくろ 和食料理店 行灯)
(同じく ざくろ 和食料理店 メニュー品書き)
日本橋の「ざくろ」は、しゃぶしゃぶ鍋の草分け的な存在の老舗料理店で、昭和30年代に創業された。日本橋店は先頃閉めてしまったが、現在銀座、室町コレド、赤坂TBSに三店舗を構えている。数年前、バイク呉服屋も銀座店で食事をしたことがあったが、民芸調の店の入り口には、芹沢が設計した行灯が置かれ、芹沢が染めた暖簾が掛けられていた。また店内には、棟方志功や浜田庄司の作品も見られる。
芹沢の仕事は、染モノの域をとっくに越えて、インテリアやエクステリアにおいても、個性あふれる優れたデザインを沢山残している。屏風や行灯などの小さなものから、美術館(倉敷・大原美術館)内部の設計に至るまで、その数に枚挙の暇がない。これほど美の領域で幅広く作品を残したのは、芹沢銈介を置いて他には見つからず、まさに芸術の巨人と呼ぶに相応しい人物であったように思う。
最後に、うちの店内に飾ってある芹沢の型絵染額をご覧頂こう。連山の間に、鳥と蝶と魚と梅花を描いている。地色は藍色で、生地は紬。山の連なりと四季折々の花鳥との組み合わせは、ポピュラーな芹沢図案と言えようか。
今日は「用の美」をテーマに、様々な芹沢銈介の作品をご覧頂いたが、少しでも皆様に型絵染の魅力と、芹沢という人物の壮大さを感じ取って頂けたら嬉しい。紹介したい作品は山ほどあり、簡単に終われるものではない。いつか機会を設けて、続きの話をしたいと考えている。最後に、芹沢が生涯の師と仰いだ柳宗悦の言葉で、稿を終えよう。
芹沢は立場をくずさない質で、いつも沈黙しているが、考えがぐらつかない。いつも謙虚で控えめなところが、私たちの尊敬を集める。あれだけ仕事をしていて、世間から認められないのは、自分を広告しないから。世渡りが下手なのは、仕事への気持ちが一筋な証拠でもある。報いが今は乏しくとも、いつか仕事は勝負を定めるだろう。(民藝76号 1937・昭和12年6月)
師は芹沢のことを、光が当たる前に正しく評価し、未来の姿を正しく予測していた。
陶磁器の金継ぎと同じように、使い続けている中で、「どうしても、直したい」キモノや帯があります。世代を繋いで使う振袖や留袖は、汚れを落とし、寸法を直しながら、晴れの日の出番を待ちます。そして、着尽くされたカジュアルモノは、着ていた母や祖母の姿を思い起こしながら、手を入れて、再び品物に命を吹き込みます。
直しを依頼される方々の品物を愛する気持ちは、請け負う側の呉服屋の心にも、何とか使えるようにしなければという気持ちを喚起させます。モノを大切にし、慈しむ気持ちを持つ方がおられる限り、和の装いは簡単に廃れない。そう思います。
今日も、最後まで読んで頂き、ありがとうございました。